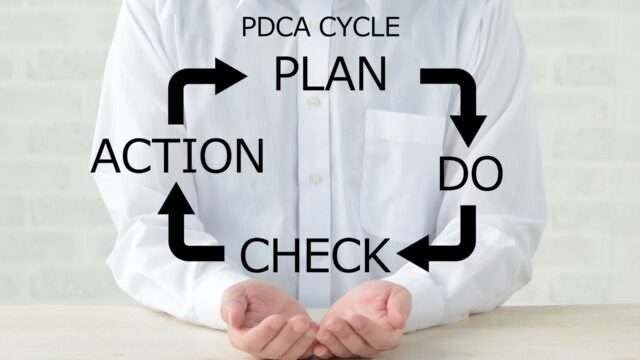上司に「指示待ち人間」と言われて、働き方を改善したいと思った経験はありませんか?仕事がうまくいかないと、そんな悩みも出てきますよね。
でも、具体的にどうすれば良いのでしょうか。何から行動すれば良いかわからず、モヤモヤしている人もいるでしょう。
この記事ではそんなあなたに、「指示待ち人間を改善する具体的な行動」について説明しています。この記事を読めば、あなたもすぐに行動できるでしょう。
改善のきっかけがつかめれば良いので、記事に書かれていることをすべてやる必要はありません。最後まで読んでみて、まずはどれか1つでも行動してみてください。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2262416)
指示待ち人間を改善する7つの行動
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23121871
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23121871さっそく、指示待ち人間を改善する行動を7つあげてみましょう。その7つとは、以下になります。
- 指示の意図を確認する
- 報連相の回数を増やす
- プラスアルファを加える
- 理想の人をまねる
- コミュニケーションを増やす
- 1日1個、小さく行動する
- 先延ばしをやめる
この記事では、特に明日から簡単にできる具体的な行動を選定しています。
ただし、上の7つは「そのままやれば良い」というわけではありません。相手に合わせるなど、時と場合を考えて行動することが必要になります。
次の章から1つずつ詳しく見ていきますので、使う相手やタイミングをイメージしながら読んでみてください。
指示待ち人間を改善する行動① 指示の意図を確認する
指示待ち人間を改善する行動の1つ目は、「指示の意図を確認する」です。
言われたことをしっかりやるのは大切です。しかし、言われたことをそのままやっているだけでは、自分が指示を出す側になったときに何もできなくなってしまいます。
「なぜこれをやるのか」「なぜこのやり方なのか」、気になったことはできるだけ確認するようにしましょう。
指示の趣旨や背景がわかると、結果のずれが少なくなります。上司のイメージに近い仕事ができて、自分で考える力もつくのでおすすめです。
指示待ち人間を改善する行動② 報連相の回数を増やす
指示待ち人間を改善する行動の2つ目は、「報連相の回数を増やす」です。
普段上司とあまり話していない人は、報連相(ホウレンソウ)の回数を増やしてみましょう。会話のやり取りが多いと、状況を把握しやすいので上司も安心できます。
また、早めに報告してフィードバックをもらうことで、修正手間が最小になるメリットもあります。効率よく仕事ができるようになるので、上司との距離も縮まるでしょう。
ただし、報連相のタイミングには気を付けてください。上司も時間に余裕がないと聞く体制がつくれないので、相手の状況をよく観察することが大切です。
指示待ち人間を改善する行動③ プラスアルファを加える
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3903601
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3903601指示待ち人間を改善する行動の3つ目は、「プラスアルファを加える」です。「言われた以上のことをやる」という気持ちで仕事しましょう。
上司は、自分より広範囲の仕事を把握しなければいけません。上司が指示しきれないことや、気づかないこともあるでしょう。
日々の仕事のなかで、「こうした方がもっと良くなる」ということを探してみてください。上司に「言わなくても気づいてくれる人」と思われれば、信用して任せてもらえるようになるでしょう。
ただし、仕事の意図を理解して行動しないと「勝手な事をするな」と言われてしまう可能性もあります。逆効果にならないように、注意してください。
指示待ち人間を改善する行動④ 理想の人をまねる
指示待ち人間を改善する行動の4つ目は、「理想の人をまねる」です。
自分のまわりにいる「うまくいっている人」の行動を観察してみてください。自分が思ったよりも、考えて動いているのがわかるでしょう。
まわりの人の言動や考え方など、良いと思ったものはどんどんまねしてみましょう。どのように考えたのかなど、本人に聞いてみるのもおすすめです。
まねすることを恥ずかしいと思う人もいるかもしれません。しかし、まねすることは相手をリスペクトすることであり、自分にとっても成功の近道なのです。
指示待ち人間を改善する行動⑤ コミュニケーションを増やす
指示待ち人間を改善する行動の5つ目は、「コミュニケーションを増やす」です。
仕事ができないと、コミュニケーションもとりづらくなってしまいます。そうならないように、できるだけまわりの人と気軽に話して、もっと自分を理解してもらいましょう。
「コミュニケーションに自信がない」という人もいるでしょう。そういう人には、コミュトレがおすすめです。
コミュトレは、コミュニケーションを学習するプログラムです。今まで習ったことのない「コミュニケーション力」を体系的に学ぶことができるので、興味があれば試してみましょう。
コミュニケーションは「才能」ではなく、後からでも身につけられる「スキル」です。しっかりとした知識やテクニックを学べば、だれでもうまく話せるようになります。
「コミュニケーションの質が人生を左右する」と言われるぐらい、コミュニケーションは大切なものです。自分の将来を考えて、一度じっくり学んでみるのも良いでしょう。

指示待ち人間を改善する行動⑥ 1日1個、小さく行動する
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/24118697#goog_rewarded
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/24118697#goog_rewarded指示待ち人間を改善する行動の6つ目は、「1日1個、小さく行動する」です。
大きく行動する必要はありません。いつもと少しだけ行動を変えてみて、上手くいったら次の行動をするようにしましょう。
行動することで、今まで気づかなかったことに気づくようになります。小さく行動すれば、結果が悪くてもすぐに修正できるでしょう。
寝る前などに「今日は何か新しいことをしたか?」と考えてみてください。「明日はこうしてみようかな」と考えて行動すれば、きっと改善に向かうでしょう。
指示待ち人間を改善する行動⑦ 先延ばしをやめる
指示待ち人間を改善する行動の7つ目は、「先延ばしをやめる」です。
人間関係がうまくいっていないと、思ったことも言えないし、行動もできません。でも、何もしないとますます「指示待ち人間」と言われてしまいます。
思いついたら、迷ってしまう前に行動しましょう。自分に迷うスキを与えてはいけません。
行動すると、まわりからなにかしらの反応があります。自分で状況が変わっていることが実感できれば、さらにはやく行動できるでしょう。
できることを全てやって、それでもダメなら仕方がない
ここまで、指示待ち人間を改善する行動を見てきました。しかし、状況によってはうまくいかないことがあるのも事実です。
一度「指示待ち人間」のレッテルを貼られてしまったら、そのイメージを変えるのは難しいでしょう。
やるだけやってダメな場合は、あきらめることも必要です。いまの会社がすべてではないので、転職も含めて検討しましょう。
ただし、転職した先でうまくいくとは限りません。いまの会社で上の7つの行動をしてみて、「行動すれば変わる」という感覚だけでも身につけるようにしましょう。


まとめ:改善のためには「行動あるのみ」
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/4847539
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/4847539今回は、「指示待ち人間を改善する行動」について説明しました。
上司に「指示待ち人間」と言われないようにするには、自分が行動するしかありません。できるだけ小さく、そしてたくさん行動して、改善のきっかけをつかみましょう。
まずは明日、7つの行動のうち何か1つをやってみることから始めてみてください。この記事を読み終わったら、ToDoリストやカレンダーに「○○をする」と書きこみましょう。
くり返しになりますが、状況は勝手に良くなりません。行動して、自分で状況を変えていきましょう。