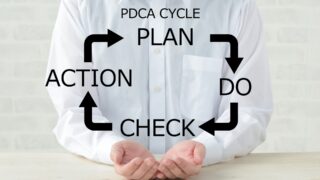あなたは上司から「自分で考えて動け」と言われたことがありませんか?気づかないうちに自分が『指示待ち人間』になっているかもしれません。
自分としては頑張っているつもりなのに、『指示待ち人間』と言われ成果も出ないと落ち込んでしまいますよね。「こんなはずじゃなかったのに、どうすれば良いの?」と悩んでしまいます。
この記事ではあなたが本当に『指示待ち人間』になってしまったのか、『指示待ち人間』の特徴と原因について紹介します。
この記事を読めば自分が『指示待ち人間』かどうか気付くことができます。『指示待ち人間』から脱却するために意識すべきことについても触れていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/22363304?title=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%80%E7%94%B7%E6%80%A7&searchId=139905670)
指示待ち人間とは
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81-%e7%94%b7-%e6%b5%b7%e6%b4%8b-%e5%b1%8b%e5%a4%96-%e7%a0%82-1836597/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81-%e7%94%b7-%e6%b5%b7%e6%b4%8b-%e5%b1%8b%e5%a4%96-%e7%a0%82-1836597/『指示待ち人間』とはどのような人のことを言うのでしょうか?この記事では『指示待ち人間』を「上司の指示がないと仕事ができない人、自分で考えて行動できない人」と定義したいと思います。
『指示待ち人間』になってしまうと、「思ったように仕事ができない」「うまく人間関係が築けない」などのデメリットが出てきます。
『指示待ち人間』には、自分の性格や会社の環境などが大きく影響しています。そのため、みんなが同じように納得できる「こうすれば良い」という具体的な解決策がありません。

指示待ち人間の3つの特徴
では、どういう人が『指示待ち人間』になってしまうのでしょうか?指示待ち人間によく見られる特徴を3つ、以下にあげてみます。
思考停止している
自分の役割を理解していない
合理主義
次の章から指示待ち人間の3つの特徴について、1つずつ詳しく見ていきたいと思います。
自分では無意識で、言われてはじめて気づくようなこともあるかと思います。自分が当てはまるかどうかを考えながら、読んでみてください。
指示待ち人間の特徴① 思考停止している
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/4849314
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/48493141つ目は「思考停止している」です。『指示待ち人間』は言われたことしかしていないので、必然的にできる業務が少なくなります。
そのため自分のできる範囲から外れるようなことが起こると、何をどうしたら良いのかわからず思考が停止してしまいます。その結果、上司に「どうしたら良いですか?」と丸投げしてしまうのです。
自分で調べたり考える様子もなく丸投げされた上司は、当然あなたに仕事をお願いしなくなるでしょう。
どんな経験のある人でも、はじめからすべて分かっている人などいません。上司に頼ることも必要ですが、自分なりに考える姿勢がないと知識や経験は得られないでしょう。
指示待ち人間の特徴② 自分の役割を理解していない
2つ目は「自分の役割を理解していない」です。仕事は組織や相手があり、1人でできるのものではありません。
「自分は頑張っている」という人がいますが、その頑張りは正しい方向のものなのでしょうか。自分が一生懸命に続けている頑張りは、会社や上司の考えと合っていますか?
会社には存在するための目的があり、目標があります。その目的や目標を理解しようとせずに自分がやりたいようにすれば、自分の役割は果たせずうまくいかなくなるでしょう。

指示待ち人間の特徴③ 合理主義
 https://www.photo-ac.com/main/detail/1672902?title=%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%BA&searchId=3464887659
https://www.photo-ac.com/main/detail/1672902?title=%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%BA&searchId=34648876593つ目は「合理主義」です。「合理主義」は人間性や性格の話で、自分にとって効率の良い働き方を目指すという考え方です。
まわりからどう思われても気にせずに、より合理的な働き方をしようとする人がいます。まわりから「協調性がない」と思われても、本人がお金を稼げれば良いと思っているので改善はされません。
合理主義は自分で希望して『指示待ち人間』になっています。自分にとっては良いのかもしれませんが、まわりは迷惑なのでうまくいかなくなるでしょう。
指示待ち人間がまわりに与える影響
もし同じ組織に『指示待ち人間』がいた場合、組織はどうなるでしょうか。指示待ち人間は組織にどんな影響を与えるのでしょう。
考えられるのは、人間関係に悪い影響を与えるということです。人間関係が悪くなると、組織のパフォーマンス低下やまわりの人のモチベーション低下につながります。
『指示待ち人間』は、結果的に会社全体の生産性を下げることにつながるのです。
指示待ち人間になる3つの原因
 出典:https://pixabay.com/ja/vectors/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%94%b7%e6%80%a7-%e6%99%82%e8%a8%88-%e6%99%82%e9%96%93-6719390/
出典:https://pixabay.com/ja/vectors/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%94%b7%e6%80%a7-%e6%99%82%e8%a8%88-%e6%99%82%e9%96%93-6719390/ところで、実力を発揮してくれると期待して採用した人たちが、どうして『指示待ち人間』になってしまうのでしょうか?
今までは指示待ち人間の特徴やまわりに与える影響を見てきましたが、次は「指示待ち人間になる原因」を3つあげてみたいと思います。
- 仕事や働き方の知識がない
- 上司に問題がある
- 会社の方針・風土に問題がある
次の章から1つずつ説明していきます。「指示待ち人間の3つの特徴」と同じように、自分が置かれている環境と照らし合わせながら見てみましょう。

指示待ち人間になる原因① 仕事や働き方の知識がない
まず1つ目は「仕事や働き方の知識がない」です。そもそもの話として、今の業務に対する知識が不足しているのは大きいと思います。
記事の最初にも書きましたが『指示待ち人間』は基本的にできる業務が少ないです。それは業務について知識の少なさが原因の1つだと考えられます。
「できないことはまず自分で考える」というクセをつけないと、何かあった時にまわりの人を頼るしかなく知識を得られません。できることが増えずに、次第に『指示待ち人間』になってしまうでしょう。
指示待ち人間になる原因② 上司に問題がある
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e4%bb%95%e4%ba%8b-%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%b3-%e7%94%b7-%e6%88%90%e5%8a%9f-2879465/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e4%bb%95%e4%ba%8b-%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%b3-%e7%94%b7-%e6%88%90%e5%8a%9f-2879465/2つ目は「上司に問題がある」です。上司の働き方があなたの働き方にとても大きな影響を与えます。
例えば「上司があいまいな指示しかしない」「すぐに怒る」「自分のやり方以外認めない」など上司の言動で、正しいことがわからなくなってしまうこともあるでしょう。
また、上司が優秀過ぎてもうまくいきません。上司の中には指示が細かく具体的で、自分ですべてを把握しておきたいという人がいます。
先回りしてすべてを整えてしまうので、部下は言うことを聞いているだけでうまくいきます。その結果、部下は「指示待ち人間」になってしまうのです。

指示待ち人間になる原因③ 会社の方針・風土に問題がある
3つ目は「会社の方針・風土に問題がある」です。会社が主体性をもって働く仕組みを作れていない場合があります。『主体性』の意味を調べてみると、以下のように書いてありました。
自分の意志・判断で行動しようとする態度。
引用:weblio国語辞典(https://www.weblio.jp/)
目的を考えて必要なことを自分で判断し、責任を持って行動するのが主体性のある人だと考えられます。しかし、会社がそういう社員を育てられていない現状があります。
そもそもの話、上司が会社からの指示で動く『指示待ち人間』だったりするのです。
指示待ち人間から脱却するために意識することは?
 出典:
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89-%e8%80%83%e3%81%88-%e6%8f%8f%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%9f-3699939/
では『指示待ち人間』を脱却するためには、どうすれば良いのでしょうか。自分で考えて動けるようになるために、すべき意識と行動を以下にあげてみたいと思います。
- まず自分で考えるクセをつける
- 知識を増やす
- 小さく行動してみる
まず自分で考えるクセをつける
何かわからないことがあった時にすぐに誰かに頼らずに、まずは自分で考えるクセをつけましょう。「自分ならこうする」という意見をもって相談するようにすれば、相手の反応も変わってきます。
意見が採用されれば自己肯定感が高まりますし、意見を出すことでより良い決定をする選択肢も増えます。それを繰り返していけば、仕事も自分自身も良い方向に進むでしょう。
知識を増やす
自分の仕事にもっと興味を持ち、知識を増やしましょう。自分の仕事だけじゃなく、ビジネススキルの知識を増やすのもおすすめです。
仕事ができる人やうまくいっている人をマネしてみると、うまくいくことが増えて自分の生活が充実してくるでしょう。
小さく行動してみる
たとえいろいろ考えていたとしても、何も行動しなければ変わりません。相手から見たら、何もしていないのと同じです。
小さなことでも行動してみると、少しづつでも状況が変わります。小さく行動すれば結果が悪くても軌道修正できるので、気楽にやってみましょう。

まとめ:小さなことをコツコツ積み上げよう
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%81%8a%e9%87%91-%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%b3-%e6%8a%95%e8%b3%87-%e4%bb%95%e4%ba%8b-2724241/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%81%8a%e9%87%91-%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%b3-%e6%8a%95%e8%b3%87-%e4%bb%95%e4%ba%8b-2724241/今回は『指示待ち人間』の特徴と原因について、さらに指示待ち人間を脱却する意識や行動についてもご紹介しました。
「自分で考えて動ける人になる」と言っても、人それぞれ自分に合ったやり方があります。毎日の生活の中で少しずつチャレンジを繰り返し、自分に合ったやり方を見つけていきましょう。
『信用』は毎日の積み重ねの結果に得られるものです。ハードルをできるだけ下げたところから毎日少しづずつ積み重ねていけば、いずれ大きな結果を得ることができるでしょう。