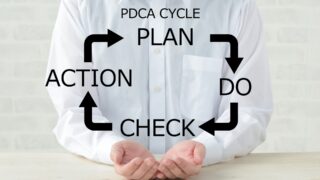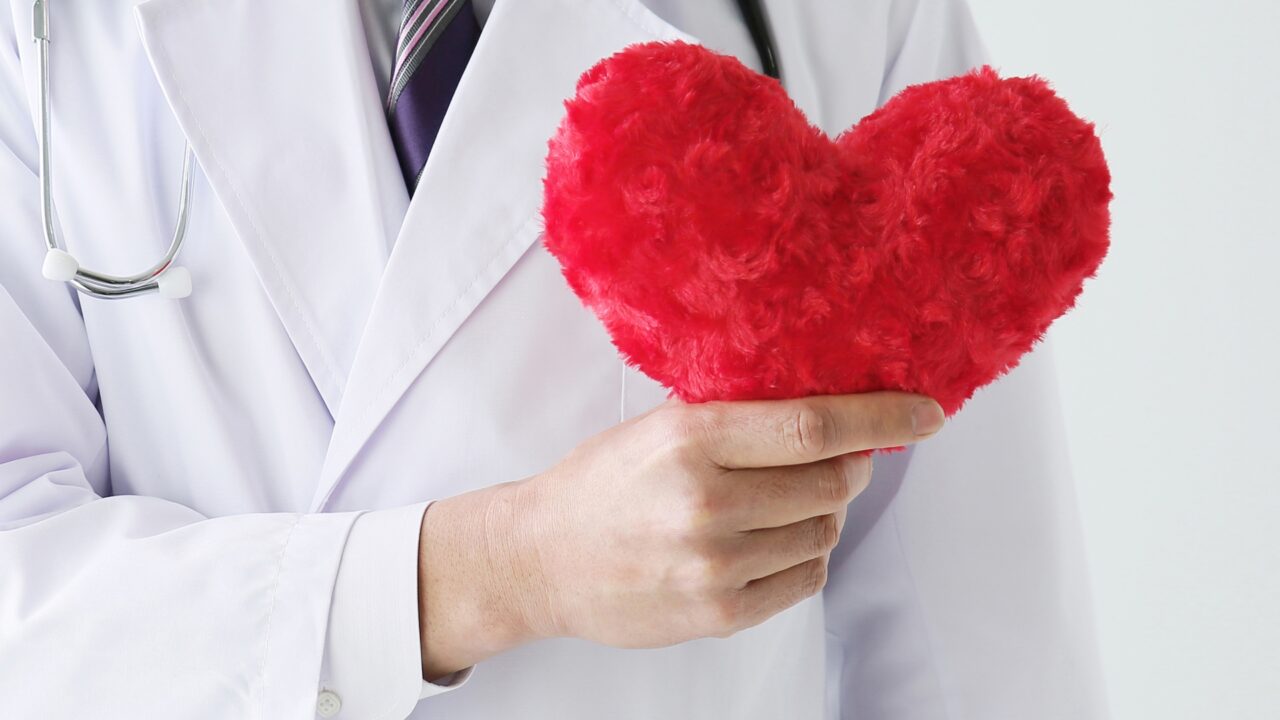あなたは普段の行動で「自分は病気かもしれない」と不安に思ったことはありませんか。仕事で「指示待ち人間」と言われて上手くいかないことが続くと、「もしかしたら」と病気を疑ってしまいますよね。
実際に、社会人になってから生きづらさを感じ、「大人の発達障害」と診断される人は多いです。
この記事では、上手くいかなくて病気かもしれないと思っているあなたに「指示待ち人間の原因となりうる病気」について説明しています。この記事を読めば、不安を解消するためにすべき行動が分かるでしょう。
仕事を続けるために「自分でできる工夫」なども紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/928617)
指示待ち人間は病気なのか
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3813422
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3813422仕事で指示待ちになってしまうのは、自分が病気だからでしょうか。結論から言うと、「指示待ち」になるのは病気だからとは限りません。
指示待ちになってしまうは、会社の環境や上司のマネジメントのせいであることもあります。病気ではなく、自分の性格などが理由の場合もあるでしょう。
また、次の章から説明する「大人の発達障害」と呼ばれるものは、白黒はっきりするようなものではなく、「傾向が強い」などグレーソーンが多く存在しています。
上手くいかないことが多いと「きっと自分は病気なんだ」と思い込みが強くなってしまいますが、まずは病気とは決めつけないで読み進めていきましょう。

指示待ち人間の原因となりうる病気3選
ここからは「指示待ち人間の原因となりうる病気」を3つ説明します。その3つとは、以下のようになっています。
- 自閉症スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 学習障害(LD)
これらは3つとも「発達障害」と言われるものになります。発達障害は「脳機能の発達に偏りが見られる障害」です。
ただし「病気」とは健全なものに対して異常があることですので、発達障害は病気というより「生まれ持った脳の特性」と言った方が良いでしょう。
発達障害は、上の3つのうち複数があわさって発症しているケースもあります。また、不安やストレスでうつ病や不安障害などの二次障害が出る可能性もあるため、早めに対策が必要です。
病気① 自閉症スペクトラム症(ASD)
では「指示待ち人間の原因となりうる病気」について、1つずつ詳しく見ていきましょう。まず1つ目は「自閉症スペクトラム症(ASD)」です。
自閉症スペクトラム症は自閉症やアスペルガー症候群、広汎性発達障害などの総称です。自閉症スペクトラム症の人には、以下のような特徴があります。
- 空気を読んだり、あいまいな表現が苦手
- こだわりが強い
- 臨機応変な対応が苦手
仕事の中では「他人と上手くコミュニケーションがとれない」「急なスケジュール変更に対応できない」などの支障が出てきます。
「普通だったらこうするよね」と言われるその「普通」がわからない場合が多いのです。
病気② 注意欠如・多動症(ADHD)
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af-4405973/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af-4405973/指示待ち人間の原因となりうる病気の2つ目は「注意欠如・多動症(ADHD)」です。注意欠如・多動症の人には、以下のような特徴があります。
- 注意力が持続しない
- 時間の管理が苦手
- 物事に優先順位をつけられない
- 整理整頓ができない
仕事では「朝寝坊を繰り返す」「物忘れやケアレスミスが多い」などの支障があります。いつも必要以上にバタバタしていて、その結果何もしていないのに疲れてしまうことが多いでしょう。
上のような症状は、普段仕事していると日常的に見られるものだと思います。普段「ドジな人だなあ」と思っていたら、もしかしたら発達障害なのかもしれません。
病気③ 学習障害(LD)
指示待ち人間の原因となりうる病気の3つ目は「学習障害(LD)」です。学習障害の人には、以下のような特徴があります。
- 単語をまとまりで認識できない
- 漢字を正しく覚えられない
- 形や音が似ている文字を読み間違える
仕事では「人の顔をなかなか覚えられない」「簡単な計算などを間違える」などの支障があります。学習に関する特定の能力が欠けているので、仕事の基礎となる能力がないと見られてしまうでしょう。
自分はやる気があるのに「やる気がなくて、仕事をきちんとやらない」と思われてしまう可能性がある病気です。
病気なら「指示待ち人間」は治る?
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23311276
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23311276これまでは、指示待ち人間の原因となりうる病気について見てきました。では、病気だった場合に、治療すれば「指示待ち人間」は治るのでしょうか。
結論から言うと、発達障害という病気を治すのは難しいです。病気というより特性なので「上手く付き合っていく」ということになるでしょう。
現状、発達障害の治療方法として考えられるのは、以下の2種類となります。
- 薬物療法
- 生活療法
薬物療法
「注意欠如・多動症(ADHD)」については、不注意・多動・衝動の症状をやわらげる薬があります。「治す」ではなく、あくまで「やわらげる」なので、緩和させることが目的です。
自閉症スペクトラム症(ASD)と学習障害(LD)については、直接的に効果がある薬はまだありません。
ただし、うつや不安障害などの二次的な疾患がある場合は、それらに対して薬を使用することが考えられます。
生活療法
自分の特性を理解する「心理教育」や、社会生活に必要な行動の仕方を学ぶ「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」などがあります。
自分の気持ちや思考のクセを理解し、衝動的な行動を抑制することで生活がしやすくなります。「カウンセリング」と言うと、イメージしやすいのではないでしょうか。
指示待ち人間が病院を受診するメリット
自分が病気かもしれないと思った場合、病院で診てもらうことにはどんなメリットがあるのでしょうか。
病院で診てもらうことで、不安は軽減され気持ちは楽になるでしょう。病気であれば、仕事で「やる気がない」「努力が足りない」と言われて辛い思いをすることを回避できるようになります。
その他にも、病気だとわかった場合には以下のような補助があります。
- 自立訓練などの障害福祉サービスが受けられる
- 医療費の自己負担額が軽減される
- 障害者手帳で税金等の割引が適用される
- 生活や仕事に支障が出た際に障害年金が支給される
病気だった場合について書きましたが、病気ではないと診断された場合でも「病気だと思っていた不安から解消される」というメリットがあります。
指示待ち人間が病院に行くタイミングは?
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23221998#goog_rewarded
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23221998#goog_rewardedでは、どのようなタイミングで病院を受診するのが良いのでしょうか。自分が不安を感じた時に行くのが良いと思いますが、遅くても「二次障害を併発する前、または直後」には行くべきでしょう。
病院は、精神科か心療内科を受診することになります。しかし、過去に「発達障害は子どもの病気」と思われていたことから、「大人の発達障害」を診てくれる病院は意外と少ないのが現状です。
都道府県や市町村で医療機関のリストや相談窓口を公開している場合もありますので、それらを頼りに病院を探してみると良いでしょう。
仕事を続けるために自分でできることを考えよう
病気かどうかは別として、仕事を続けていくためには自分の特性と上手く付き合っていくしかありません。ここでは「特性にあわせて自分でできる工夫」について、3つ紹介したいと思います。
- メモを活用する
- モノを少なくして、しまう場所を決める
- 物事をする時間を決める
メモを活用する
することや思ったことなどはメモに書いておき、脳は「考えること」に使いましょう。「覚えておく」ことはメモに任せてしまうのです。
これは仕事ができる人がよくしているやり方です。定期的にメモを見る習慣ができれば、気づいたときにメモを取って整理しておくことで物忘れをなくすことができます。
モノを少なくして、しまう場所を決める
モノが多いと整理も大変なので、できる限り少なくしましょう。しまう場所も余裕をもって決めてしまえば、すべきことが明確になって楽になります。
モノが少ないとすっきりして、集中力が増すという効果もあります。捨てるルールを決めたりデータ化して保管したりするなど、モノを減らす工夫をしましょう。
物事をする時間を決める
時間を決めて習慣にしてしまうと、意識して頑張ろうとしなくてもできるようになります。例えば歯磨きのように「このタイミングになると自然にする」状態を目指すのです。
習慣化するには、なにか他のことにヒモづけして行うと良いでしょう。歯磨きなら「ご飯を食べた後に」や「お風呂に入る前に」など、別の行動とセットにするとうまく続けられます。
指示待ち人間でも、自分の特性を理解して働こう
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23279410
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23279410今回は「指示待ち人間の原因となりうる病気」について説明しました。
くり返しになりますが、発達障害は病気いうより特性です。自分の特性を理解して、対処法を考えることが大切になります。
状況によっては、まわりに説明して理解してもらうことなども必要になると思います。自分の特性に合った働き方を考えて、行動していきましょう。
「病院を受診する」「自分で工夫できることを実践してみる」など、まずは不安を解消するために行動をはじめてください。自分ができることから、少しずつ状況を変えていきましょう。