あなたのまわりに「指示待ち人間」だと思う人はいますか。あなたはどういう原因・不満があって、その人をそう呼ぶのでしょうか。
それがもし自分に向けられた場合、あなたは自分が「指示待ち人間」と言われる原因がわかるでしょうか。自分はそんなつもりで仕事していないので、おそらく原因が分からず悩んでしまいますよね。
この記事では、そんなあなたに「指示待ち人間」と言われる5つの原因を説明します。この記事を読めば、「指示待ち人間」と言われる原因がわかり解決の糸口がつかめるでしょう。
「指示待ち人間」はまわりから信用を失ってしまっている状態です。少しずつ行動を積み重ねて信用を回復する必要がありますので、すぐに行動できるように最後までしっかりと読んでください。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/3813422)
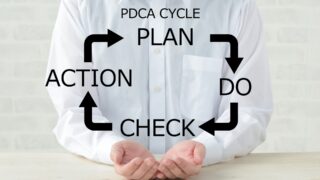
指示待ち人間と言われる5つの原因
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6-%e8%b5%b7%e5%8b%95-%e7%94%b7-%e8%a8%88%e7%94%bb-%e4%bb%95%e4%ba%8b-593358/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e5%ae%b6-%e8%b5%b7%e5%8b%95-%e7%94%b7-%e8%a8%88%e7%94%bb-%e4%bb%95%e4%ba%8b-593358/「指示待ち人間」と言われる原因には、「自分の内面的なもの」と「仕事の人間関係」の2種類があります。それをふまえて5つの原因を以下にあげてみます。
- 自分の内面的なもの
- 自分の価値観
- 過去の経験
- 仕事への姿勢
- 仕事の人間関係
- 上司との関係
- 会社の人達との関係
次の章から1つずつ詳しく見ていきます。1つ注意点を言うと、新人やその仕事をして日が浅い人は「指示待ち人間」とは言いません。
新人やその仕事をして日が浅い人は、仕事を教えてもらって覚えなければいけません。仕事を覚えるために、指示に従って動くのが当たり前なのです。
この記事でいう「指示待ち人間」は、ある程度の期間その仕事をしていて、その中でうまくいかない人のことを言っています。

指示待ち人間と言われる原因① 自分の価値観
指示待ち人間と言われる原因の1つ目は「自分の価値観」です。価値観とは、その人なりの判断基準のことを言います。
「指示待ち人間」になる人は、まわりに頼って助けられて来た経験が多く、自分に甘い人が多いと考えられます。それはある意味では環境に恵まれて育ったとも言えます。
しかし、仕事では「自分でなんとかしようという気持ちが少ない」「やる気を感じられない」というような評価になってしまいます。
価値観は自分の人間性として現れますので、あなたは普通にしているつもりでもまわりは違和感を感じます。その違和感が「指示待ち人間」と言われてしまう状況につながるのではないでしょうか。
指示待ち人間と言われる原因② 過去の経験
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23120965
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23120965指示待ち人間と言われる原因の2つ目は「過去の経験」です。わかりやすい例で言うと、「指示以外のことをしたら『勝手なことをするな』と怒られた」などです。
これは後に出てくる人間関係とも関連することですが、自分が考えて動いたときに相手の気持ちとかみ合っていないことが原因です。
このような経験が積み重なると自分から何かするのがこわくなり、言われたことだけをするようになります。自然にリスクを回避するようになるのです。
リスクを最小限にするために言われたことだけをする日々を送れば、後に「指示待ち人間」と呼ばれてしまうのは容易に想像できるでしょう。
指示待ち人間と言われる原因③ 仕事への姿勢
指示待ち人間と言われる原因の3つ目は「仕事への姿勢」です。あなたの仕事は、上司が評価することになります。
上司に良く評価してもらうためには、仕事へのやる気を見せたり、自分の役割を理解して行動しなければなりません。
しかし「指示待ち人間」と言われる人は、仕事の目的や自分の役割を理解していないことが多いです。仕事の一部分である自分の業務しか見ていないと、仕事を効率的に進めることはできないでしょう。
結果的に「やる気がない」「わかっていない」などの評価になり「指示待ち人間」と言われてしまいます。言われた本人は具体的に何が悪いのかわからないまま、低い評価を受けてしまうのです。
指示待ち人間と言われる原因④ 上司との関係
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e4%bb%95%e4%ba%8b-%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%b3-%e7%94%b7-%e6%88%90%e5%8a%9f-2879465/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e4%bb%95%e4%ba%8b-%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%b3-%e7%94%b7-%e6%88%90%e5%8a%9f-2879465/指示待ち人間と言われる原因の4つ目は「上司との関係」です。いままでの3つは自分の内面的なものでしたが、ここからは会社の人間関係について見ていきます。
上司は「部下を育てる」ことも仕事の一つです。そのため、上司はあなたにいろいろなアプローチをします。
しかし、指示したことしかやらなかったり、期待を上回らないことが続くと、上司はあなたを信用できなくなります。仕事を任せられないと判断されると最低限の仕事しかできないため、次第に「指示待ち人間」と言われてしまうのです。
ただし、上司との人間関係に関しては、100%すべてあなたが悪いという訳ではありません。上司にもいろいろな人がいて上司に原因がある場合もありますので、そこはまわりの人の意見もふまえて考えましょう。

指示待ち人間と言われる原因⑤ 会社の人達との関係
指示待ち人間と言われる原因の5つ目は「会社の人達との関係」です。上司と同じように、会社の人達にもいろいろな人がいます。
相手の気持ちを考えずに自分が思ったままに行動すると、まわりとかみ合わずにうまくいかないことが出てくるでしょう。
例えば、「これぐらいわかるだろう」とまわりに何も言わずに進めてしまうと、連携が取れないだけでなくミスの原因になります。
まわりの人はチームが困らないように、ちょっとした声掛けなどを頻繁にしています。コミュニケーションがとれないとまわりが仕事しづらいと感じるようになり、任せられる仕事が限られることで「指示待ち人間」と呼ばれてしまうのです。

自分がどう見られているかを意識しよう
「指示待ち人間と言われる5つの原因」を説明してきましたが、ここでは番外編として「自分がどう見られているか」について考えてみたいと思います。
あなたは、以下のような状態の社員に対してどのような印象を持つでしょうか。おそらく「やる気がない」「信用できない」と思うのではないでしょうか。
- いつも眠そうにしている
- 行動が遅い
- 離席してなかなか戻ってこない
「指示待ち人間」は言われた仕事しかしていないという状態ですが、そう呼ばれることには「信用して任せられない」という気持ちもあると考えられます。あなたはいつも仕事に集中できていますでしょうか?
仕事に集中できるかどうかは、睡眠時間や朝食をきちんと食べたかなど『生活習慣』に大きく影響されます。仕事中の自分をどう見せるかも「指示待ち人間」と呼ばれることに関係してきますので、生活習慣についてもこの機会に考えてみましょう。

指示待ち人間が会社に与える影響
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%b3-%e4%bc%9a%e7%a4%be-%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9-1572059/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%b3-%e4%bc%9a%e7%a4%be-%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9-1572059/「指示待ち人間」と呼ばれるのはあなたにとって大きな問題ですが、実はあなただけの問題ではありません。「指示待ち人間」がいることは、上司や会社にとっても以下のような影響があります。
- 生産性を下げる
- 他の社員から不満が出る
- 組織体制に悩む
生産性を下げる
「指示待ち人間」がいると個人の生産性が上がらないだけでなく、組織としての生産性にも悪い影響を与えます。仕事は組織で協力して行うものが多くあるからです。
動きの悪い「指示待ち人間」は足を引っ張ることになり、組織全体の生産性が上がらない原因になってしまうでしょう。
他の社員から不満が出る
「指示待ち人間」は指示されたことしかやらないので、「自分で考えて行動する人」の仕事の負担がどんどん増えていきます。給料体系は同じなのに負担ばかり増えて、「自分で考えて行動する人」の不満がどんどんたまっていくでしょう。
そうしていくうちに人間関係も悪くなり、どんどん状況が悪化してしまいます。
組織体制に悩む
組織の人間関係が悪いと、上司も役割や体制維持に頭を痛めます。上司は「指示待ち人間」であるあなたを手放したいと思うかもしれません。
人事を考える部署でも組織体制を考えるのに苦労するでしょう。「指示待ち人間」がいることで、いろいろなバランスが崩れてしまうのです。
原因を改善していこう
ここまでの説明で、「指示待ち人間」と言われる原因が想像できてきたのではないでしょうか。ここからは、原因を改善する方法について少し触れたいと思います。
主な改善方法は以下のようになります。自分でできる行動を具体的に考えながら、見ていきましょう。
- 内省
- 知識を増やす
- コミュニケーション
内省
定期的に『内省』して、自分の内面を見つめなおしましょう。過去を反省するのではなく、分析して次の行動に生かすという意識が大切です。
例えば相手の気持ちが理解できるように、何かする前にちょっとだけ「相手の気持ちになって考えてみる」という意識を持つとします。それができているか振り返る習慣を持てば、状況は変わってくるでしょう。
知識を増やす
「仕事の内容」や「働くこと」について、知識がないことが不安を感じる原因かもしれません。知識を増やすことで不安が和らぎ、行動に移しやすくなります。
自分の仕事にこだわらず、いろいろなことに興味を持って知識を吸収していきましょう。そうすることで、いろいろな視点で物事を見る力がつきます。
コミュニケーション
仕事は人間関係がとても重要です。少しずつでもコミュニケーションをとる意識を持ちましょう。まずは笑顔で明るく挨拶をすることから始めてみてはいかがでしょうか。
また、会議に「この会議の中で1つ意見を出そう」という気持ちで参加すると、いつもと変わらない会議でも前向きに考えることができるでしょう。
まとめ:行動することで、まずは自分が変わろう
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/949605
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/949605今回は「指示待ち人間と言われる5つの原因」について説明しました。
この記事で原因を理解したら、すぐに改善する行動に移しましょう。なぜなら、自分が思っていても行動しないと何も変わらないからです。
あなたがどんなに仕事に対して考えていても、相手が勝手にそれに気づいて理解してくれるなんてことはありません。相手に気持ちが伝わるように、自分が変わらないといけないのです。
相手を変えさせるのは非常に難しいことですが、自分が変わることは比較的簡単にできます。小さなことからでも自分で行動し、それを積み重ねることで信用を回復していきましょう。



