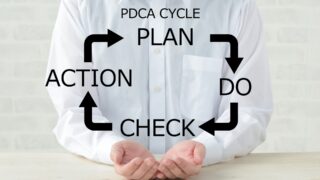あなたは自分が「指示待ち」で仕事していると思いますか?当たり前ですが、そんなことを思っている人はいないでしょう。
それなのに上司から突然「指示を待ってばかりいるな」「自分で考えて動け」と言われたら、戸惑ってしまいますよね。どうしたらいいかわからず、落ち込んでしまうでしょう。
この記事ではそんなあなたに、部下が「指示待ちになるのは当たり前」だと思える5つの理由について説明します。この記事を読めば自分が悪いわけではないことが分かり、気持ちが楽になるでしょう。
しかし、みんなが指示待ちで良いというわけではありません。いずれは「自分で考えて動く」ことが必要になることも書いていますので、最後まで読んでみてください。
(アイキャッチ画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/4613228)

指示待ちは悪いこと?
 出典:https://pixabay.com/ja/vectors/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%94%b7%e6%80%a7-%e6%99%82%e8%a8%88-%e6%99%82%e9%96%93-6719390/
出典:https://pixabay.com/ja/vectors/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%81%ae%e7%94%b7%e6%80%a7-%e6%99%82%e8%a8%88-%e6%99%82%e9%96%93-6719390/『指示待ち』という言葉は、言われた人が悪いような、ネガティブなイメージを持つと思います。まわりにも「やる気がない」「消極的」などの印象を与えるでしょう。
しかし、部下が上司の指示で動くのはごく自然なことなのです。けっして悪いことではないですし、むしろ当たり前と言えるでしょう。
チームとして機能するためには上司が適切な指示を出し、部下がそれに従って動くのが当たり前です。うまくいかないのは指示を出す側の問題と言っても言い過ぎではないでしょう。
「指示待ちになるのが当たり前」と思える5つの理由
ここからは、部下が「指示待ちになってしまうのが当たり前」だと思える「5つの理由」について見ていきたいと思います。
- 部下は仕事の経験・知識が少ない
- 部下が勝手なことをしたら上司が困る
- 部下は責任が取れない
- 上司に合わせないと怒られる
- 上司が会社の指示を待っている
ひと言で『指示待ち』と言っても、もともと仕事への意欲のない『指示待ち』と、まわりの環境のせいで『指示待ち』になってしまった人がいると考えられます。
次の章から1つずつ見ていきますので、自分の会社などを思い浮かべながら読んでみてください。
指示待ちが当たり前な理由① 部下は仕事の知識・経験が少ない
1つ目は「部下は仕事の知識・経験が少ない」です。新人や異動したばかりの社員はまだ知識や経験が乏しいため、仕事がわからないのが当たり前でしょう。
新人や異動したばかりの社員は上司から指示されて仕事をこなしていき、知識・経験を得ていきます。そのために組織があり役職があるのです。
上司は仕事の目的や方向性、考え方を部下に伝えて育てていきます。部下は上司をまねることから始めるため、とうぜん指示待ちになるのです。
指示待ちが当たり前な理由② 部下が勝手なことをしたら上司が困る
 出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e4%bb%95%e4%ba%8b-%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3-%e5%a5%b3%e6%80%a7-%e8%8b%a5%e3%81%84%e5%a5%b3%e6%80%a7-3560932/
出典:https://pixabay.com/ja/photos/%e4%bb%95%e4%ba%8b-%e3%83%ac%e3%83%87%e3%82%a3-%e5%a5%b3%e6%80%a7-%e8%8b%a5%e3%81%84%e5%a5%b3%e6%80%a7-3560932/2つ目は「部下が勝手なことをしたら上司が困る」です。上司がしっかりと仕事の目的や方向性、考え方を伝えていないと、部下は何をどうすれば良いのかわかりません。
そういう組織にかぎって、部下が何かすると上司に「勝手に動くな」「余計なことはするな」と言われたりします。
上司は「考えて動け」と言いたいのでしょう。しかし「考えて動く」では抽象的すぎて正解が分からず、結果的に部下は動けないのです。
部下が思考停止して指示待ちになってしまうのは上司が悪いとも言えるでしょう。

指示待ちが当たり前な理由③ 部下は責任が取れない
3つ目は「部下は責任が取れない」です。当たり前のことですが、仕事の方針や行動を決める決定権は上司にあります。
きちんと方針や行動についての指示がないと、部下は上司の考えや仕事の目的に合った行動ができません。
部下は変に動いてミスしても責任が取れないので、きちんと上司から指示されるのを待つことになります。真面目な部下ほど指示待ちになってしまうでしょう。

指示待ちが当たり前な理由④ 上司に合わせないと怒られる
 出典:https://pixabay.com/ja/illustrations/%e6%81%90%e3%82%8c-%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%82%8b-%e8%b2%ac%e4%bb%bb-%e6%95%b5-%e5%91%8a%e7%99%ba-4208770/
出典:https://pixabay.com/ja/illustrations/%e6%81%90%e3%82%8c-%e9%9a%a0%e3%82%8c%e3%82%8b-%e8%b2%ac%e4%bb%bb-%e6%95%b5-%e5%91%8a%e7%99%ba-4208770/4つ目は「上司に合わせないと怒られる」です。上司の中には、部下に自分の当たり前を押し付けてくる人がいます。
上司が「普通はこうだろう」と言いますが、普通とは何でしょうか?「普通」という言葉が抽象的すぎて、部下はそれを聞いても動けません。
他にも「部下の失敗やミスを許せない」「質問や意見をきちんと聞かない」など、上司に問題があることは意外と多いです。「仕事ができる」人が「部下をうまく育てられる」人だとは限らないので、仕方がないでしょう。
部下はもちろん怒られたくないので、上司の指示があるまで待つようになってしまいます。
指示待ちが当たり前な理由⑤ 上司が会社の指示を待っている
5つ目は「上司が会社の指示を待っている」です。部下に偉そうなことを言う上司がいますが、そもそも上司が会社の指示を待っている『指示待ち人間』だったりします。
人は年齢を重ねるたびに「保守的」「受け身」になっていきます。昔はバリバリ働いていた上司も、楽して稼ぐ「省エネモード」になっているかもしれません。
反対に、自分がまだ第一線で働いているプレイングマネージャーもいます。組織を管理し部下をマネジメントするよりも、自分が第一線で働きたいという人もいるのです。
そのせいで部下に充分な指導ができないことも、部下が指示待ちになってしまう原因だと考えられます。

指示待ちが当たり前なのははじめのうちだけ
 出典:https://www.pakutaso.com/20190853227post-22721.html
出典:https://www.pakutaso.com/20190853227post-22721.htmlここまで「指示待ちが当たり前と思える5つの理由」を見てきましたが、ではなぜ上司が「指示を待ってばかりいるな」「自分で考えて動け」などと言い出すのでしょう?
それは今までの理由の多くが、新人や異動したばかりの慣れていない社員に対して言えることだからです。ある程度の知識や経験を得たら、いつまでも指示待ちしているわけにはいきません。
指示待ちしていた人も、どこかのタイミングで指示を出す側になります。業務の一部を任されて、業務の課題を把握したり上司に問題提起したりしなければならなくでしょう。
あなたは部下と上司の間をつなぐ存在になり、目標を意識して上司を補佐する立場になるのです。
指示待ちをやめるために準備しよう
先ほども書きましたが、最初はみんなまねることから始めます。しかしずっとそのままでは、いつかどこかで壁にぶつかるでしょう。
あなたは『守破離』という言葉をご存じでしょうか。以下に意味を引用します。
剣道や茶道などで、修業における段階を示したもの。「守」は、師や流派の教え、型、技を忠実に守り、確実に身につける段階。「破」は、他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる段階。「離」は、一つの流派から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階。
引用:goo辞書(https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%AE%88%E7%A0%B4%E9%9B%A2/)
はじめは「守」で指示にしたがい知識・経験を得ていきますが、どこかの段階でその殻を「破」る必要があります。まねるだけでなく、自分で考えて行動するようにならなければなりません。
そのためには知識・経験とともに、「一歩先を見ようとすること」「目的・目標から物事を考えること」「仕事の幅を増やすこと」などが必要になってくるでしょう。

まとめ:自分で考える意識を持ち、行動しよう
 出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2389903?title=%E3%82%AC%E3%83%83%E3%83%84%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E7%94%B7%E6%80%A7&searchId=1054478876
出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/2389903?title=%E3%82%AC%E3%83%83%E3%83%84%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E7%94%B7%E6%80%A7&searchId=1054478876今回は「指示待ちになるのは当たり前だと思える5つの理由」を説明しました。さらに知識や経験を得て、指示待ちを脱却する準備が必要だということもお話ししました。
指示待ちは会社の環境の影響が大きいので、自分で脱却するのは大変なことだと思います。それでも、やはり最後には自分で脱却することが必要です。
そのための知識はすぐに身につくものではないので、少しずつ意識していきましょう。「次の会議で1つ質問か意見をする」など簡単なことからでも良いので、具体的に行動してください。
信用は、相手の期待を上回る結果を出し、積み上げでいくことで得られるものです。広く学び、良い習慣を身につけることで、上司から『指示待ち』と言われる段階を卒業しましょう。